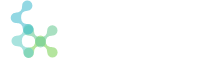Advertisements
激しい恐怖が私を襲います。教室から全力疾走しています。足音が静寂な廊下に響き渡り、心臓の鼓動が激しく、そのリズムはほとんど耳に聞こえないほどです。
数分間、手は震え続け、落ち着かせようとします。しかし、ベルが鳴ると、私は教室に戻ってリュックを取りに行かざるを得ません。
「何があったの?」と教授が尋ねます。
パニック発作についての真実を教えたい。不安に屈し、不確かな未来の重荷を肩に感じる感覚。しかし、不安について話すことで教授の時間を無駄にしたくない。彼女は前と同じように、それはすべて私の頭の中だと説明し、私を立ち去らせるだろう。
「気分が悪い」と私は納得できなく言います。「教室を出てしまってごめんなさい」
教授は私を見つめ、ティッシュを手渡します。何も言わないし、私も何も言わないが、私たちは両方とも何が起こったかを知っている。
「これがパターンになってきていますね」と彼女は言います。「誰かと話すべきかもしれませんね」
朝3時にパニック発作を起こすと、それはいつも恐ろしい経験です。
寝室を見回して自分を現実に引き戻そうとします。しかし、真夜中の真っ暗な虚無の中で、暗闇はその空虚感で私を窒息させ、呼吸が苦しいです。
ベッドの端にあるテディベアを手に取ります。生まれてからずっと持っており、あらゆる高低に寄り添ってきました。「怖い」と自分に告白しながら、彼をしっかりと握りしめます。「助けて!」
数分間、テディベアの反応を待ちます。しかし、一方的な会話は私を孤立させるような気がします。そこで、iPodを手に取り、心を落ち着かせる歌詞が私の心をなだめるのを聞きながら眠りにつきます。
数年前、私は美しい本『海辺のカフカ』を読みました。その中の一節が私に教えてくれたこと、それはいつも暗い時期には必ず明るい未来があるという希望です。
「嵐が過ぎ去ると、どのようにしてそれを乗り越えたか、どのように生き延びたかを覚えていないだろう。実際、嵐が過ぎ去ったかどうかさえわからなくなるだろう。しかし確かなことが一つある。嵐から出てきたとき、中に入った人と同じ人ではなくなっているだろう。それがこの嵐のすべてだ。」
こう考えました…
嵐は恐ろしいものかもしれません。風が強まり、葉っぱをかき乱し、野生動物は避難を求めます。しかし、すべての嵐は最終的に終わります。雨が止み、風はゆっくりと穏やかなそよ風に変わり、葉っぱをなめらかな子守唄で揺らします。
私の不安も同じだと気づきました。「嵐のように、これもすぐに終わる」と自分に言い聞かせます。 「私はこれまで経験してきたすべてを乗り越えてきたし、これも乗り越えるだろう。」
信じられないようですが、事実です。
世界保健機関によると、3億人以上が不安に苦しんでいます。「不安障害に対する有効な治療法は存在するにもかかわらず、治療を受ける人は必要な人の4人に1人(27.6%)しかいません。」
これは心を打つものです。
他に言いようがありません。
イギリスには24時間対応のメンタルヘルスヘルプラインがあります。また、不安に関連するすべてのことを話すことができる機密のサポートを提供する無料のリスニングサービスもあります。
同様のプログラムはアメリカにも存在します。たとえば、Mental Health Americaには、不安、うつ病、およびさまざまな他の精神的健康の問題に苦しむ人々のための24時間ヘルプラインがあります。
私はもっと早く誰かと話をしていればよかった。しかし、時間を巻き戻すことはできません。代わりに、私は不安に苦しむ私の若い頃のような人々が、これらのリソースを利用して孤独を感じないようになることを願っています。
そして、そのために世界はより良くなるでしょう。
学校から帰宅すると、母は暖かく私を迎えます。彼女の腕に溶け込み、彼女をしっかりと抱きしめ、彼女のシャツに涙をかけて謝罪します。
「大丈夫?」と母が尋ねます。
「違う」と私は鼻水を垂らしながら答えます。
母は私が言葉よりもっと多くを伝えているのを気づきますが、私は言葉にできないので、言葉もなく感動しています。
「大丈夫だよ」と母が約束します。「明るい日々が待っているわ。」
「そう願ってる」と私は答えます。「本当にね。」
数週間後、私は学校のカウンセラーのオフィスに座っています。私は不安について誰にでも話せることに安堵の波が押し寄せます。
「何が気になっているの?」とカウンセラーが尋ねます。注意深く聞いてくれていて、私が返答するのを待っています。
私は自分の不安についての気持ちを言葉にするのは初めてなので、数分間の休憩があります。
「誰かと話す必要がある」と私はついに認めます。「数年間、パニック発作に悩まされ、社交的な状況で麻痺してしまっています。」
学校のカウンセラーは私の目を見つめ、私が底に達したと告白するのを聞いています。彼女は中断しません。そして、何年ぶりかで初めて、誰かが気にかけてくれているように感じます。
「話すのは難しかったでしょう」とカウンセラーは私たちの話し合いの最後に言います。「でもうまくやってくれましたよ。もしもう一度誰かと話す必要があれば、知らせてね。」
ベルが鳴り、私はカウンセラーに別れを告げます。廊下を歩いていくと、頭を高く保ち、自分の血管を流れる力を感じます。